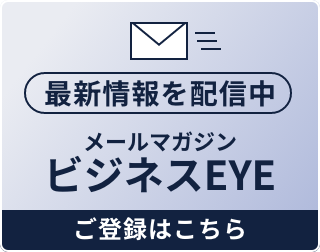生前贈与は本当に効果があるの?
効果の高い贈与の方法とは
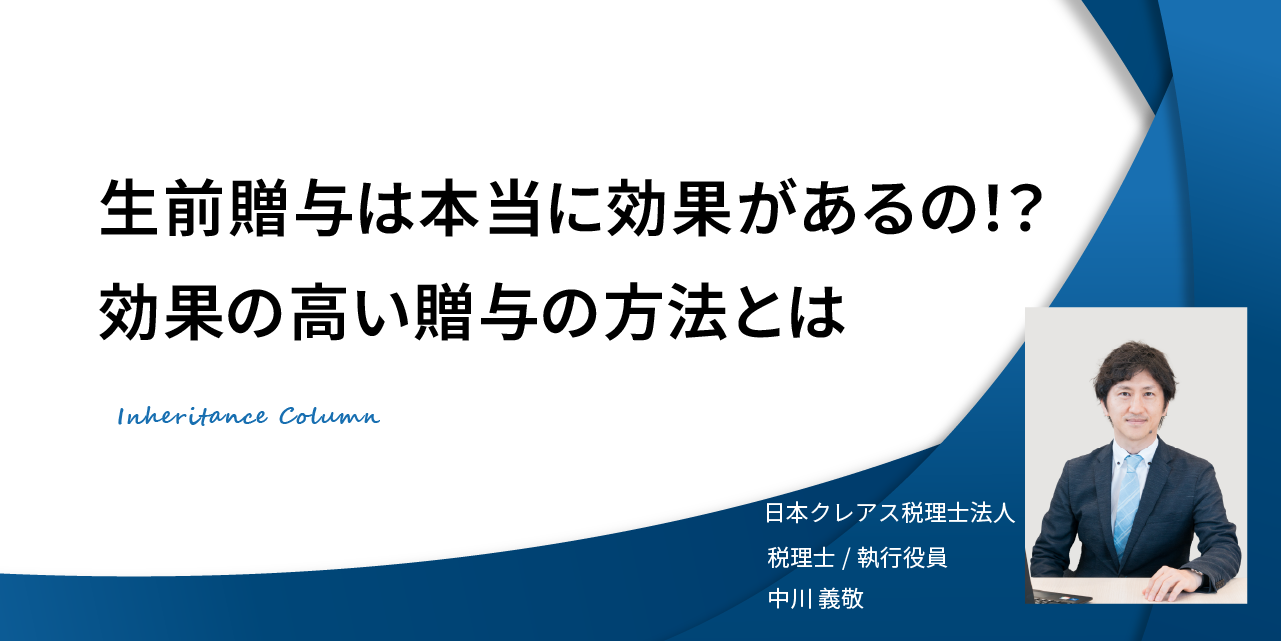
相続対策には贈与を活用することが一般的と言われています。贈与の方法には暦年贈与という方法が一般的で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を控除した金額に贈与税がかかるというものです。
贈与税は、もらった財産の合計額が基礎控除額の110万円以下であれば課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。このことから、相続税対策で生前贈与を年間110万円の範囲内で行うという方法がとられることがあります。
そこで今回は、生前贈与のメリットや贈与をする際のポイントについてご紹介いたします。
■生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている個人から財産を無償で渡すことで、もらった側には「贈与税」が課税されます。例えば親から子供にお金をあげると、贈与税の対象になりますが、それだけでなく、誕生日祝いに車などのプレゼントを贈ったり、恋人にアクセサリーをプレゼントすることも厳密にいえば贈与税の対象となるのです。
ただし、扶養義務者間で生活費などの通常必要な範囲内の費用は、贈与税がかかりません。
また、香典、祝物、お見舞いなど、社交で必要と認められるものについても贈与税は課税の対象とはなりません。
■生前贈与するメリットとは?
次に生前贈与をするメリットを見ていきましょう。
1.生前に特定の方に財産を渡すことが出来る
生前贈与は、配偶者や子供、兄弟などの相続人はもちろん、他人にも実行することが可能です。特定の方に財産を渡すことで、財産の承継先を明確にすることが出来ますし、また日頃お世話になっている人に、財産を譲ることなども可能です。
教育資金や自宅の購入、結婚のための資金であれば、税制の優遇措置も設けられているため、一定金額のまとまったお金を贈与することも可能です。
2.相続税の節税になる
将来課税される相続税を、生前贈与をすることによって節税することが可能です。
相続税は、相続が発生した時点の相続財産の総額に対して課税がされます。以下、贈与税と相続税の税率ですが、将来課税される相続税の税率よりも、低い税率の幅で贈与を行えば効果が高まります。生前贈与により、相続財産の総額を減らすことが出来るので、計画的に贈与を行う事で、将来課税される相続税を減少させる効果が生まれます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円越え | 55% | 640万円 |
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3.収益不動産の収益を移転できる
収益不動産は相続が発生するまで、収入が入り続けるため被相続人の相続財産の総額を増やすことになります。収益不動産を贈与すれば、将来稼得する予定であった収入部分を相続人に移すことが出来るため、相続税の圧縮効果が期待できます。
■生前贈与を上手に活用するポイントとは?
計画を立て行ってきたつもりの生前贈与が、定期金の贈与であるとか、名義預金であると判断されてしまうのは不本意なことです。
生前贈与が、正しく認められるために贈与者・受贈者の間で対策を行うことがポイントです。
1.贈与契約書を作成する
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が、いつ・いくらの贈与を受けるかを合意したことの証明として作成するものです。贈与が原則として双方の承諾で成立するものであることから、すべての贈与で作成しておくことが望ましいといえます。
契約は口約束でも有効なのですが、贈与の場合、その契約があったことを示すために必要となるため、必ず書面で作成しておきましょう。
2.名義預金口座の管理をおこなう
名義預金とは、贈与をしたつもりが相続財産とみなされてしまう預金口座を指します。
例えば、年少のお子さんやお孫さんなど、まだ金銭管理を任せられない相手に贈与を行うにあたって、子どもや孫名義の口座を開設し、そこにお金を振り込むことで贈与したものとするケースです。
この方法は、相手がそのような口座の存在を知らないという時点で、贈与は成立せず、口座内の預金は相続が発生すれば、その振込みをした方の相続税の課税対象となります。
名義預金の対策としても、まずは受贈者にその預金の存在を知らせる意味で、贈与契約書の作成を行います。また、名義預金とみなされないよう、口座の通帳や印鑑の管理は受贈者が行います。
口座内の金銭を管理していることを示すには、たとえば、受贈者名義の支払いの引き落とし口座に設定することなどが有効な手段になります。
受贈者が未成年者の場合は、贈与契約に親権者の同意が必要ですので、契約書の作成や、その後の通帳等の管理方法について検討が必要です。
3.生前贈与加算
生前贈与加算とは、被相続人の死亡前7年間に法定相続人が贈与された資産について、相続税の計算に含める制度です。贈与税には年間110万円の基礎控除があることから、生前贈与が相続税対策として活用されていますが、「生前贈与加算」により死亡前7年分は基礎控除枠内の贈与であっても非課税とならず、相続税が課されることになります。
法定相続人以外の方への贈与は対象外となるため、誰に贈与を行うかは、早めに決めて実行をすることが望ましいと言えます。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。