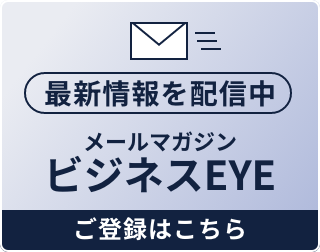遺言書は我が家には関係ない?遺言書のメリット・デメリット
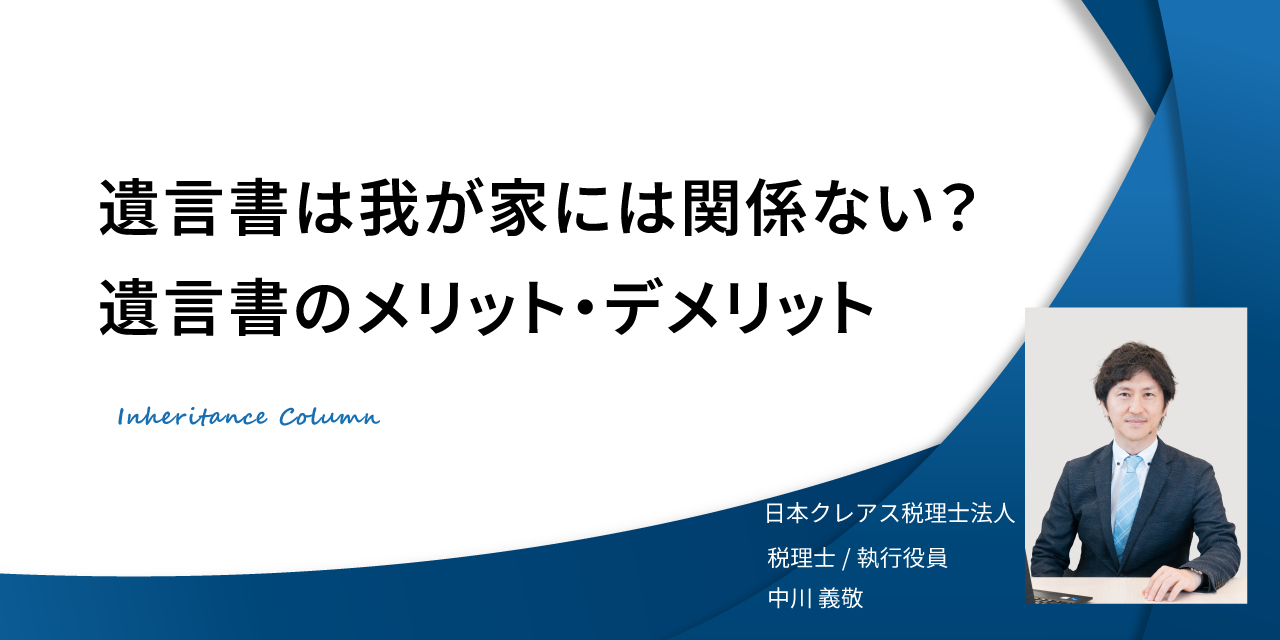
「うちには遺言を遺すほど財産は無い」、「遺言書と聞くと堅苦しいイメージがある」と思っている方が多数を占めていると感じます。
多額の財産を所有している人は、遺言もセットで相続を考えています。
一方で、相続税がかからない世帯の人にとっては、遺言も不要なものと位置づけされているように思えます。
「遺言が必要な人=多額の財産がある人」というイメージが正しくて、少額の財産しかない世帯の人に遺言は不要なものでしょうか?
今回は遺言書の基本的な内容から、そのメリット・デメリットに関してお話します。
■遺言書とは?
法律上、遺言を遺す義務は無く、遺言書の作成は任意となっているので、遺言をするかしないかは個人の自由です。
相続が発生した場合、「残された財産を誰が貰うのか?」という問題は、財産が多額であるかどうかは関係なく、全ての相続について回ることです。
遺言書は、遺産分割で家族がもめないための重要な意思表示です。
■遺言書の種類
遺言書は大きく「普通方式」と「特別方式」に分けられ、「普通方式」はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3つの種類に区分されます。
ここではよく利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明します。
◇自筆証書遺言
遺言者が自分で作ることができるのが、自筆証書遺言です。
紙とペンと印鑑があれば作成でき、最も簡単な方法といえます。
しかし、本人が書いたものかを証明することが難しい、遺言書が発見されない、などの恐れもあります。作成の流れは、以下のとおりです。
- 遺言書本文を自筆する
- 作成日付を記す
- 遺言者本人が署名捺印をする
訂正や加筆、削除をするときにも決まりがあるので、決まったルール以外で訂正などを行うと遺言の効果が無効になってしまいます。
従来は自筆証書遺言を作成したら、自宅に保管をする方法が一般的でした。 しかしこれでは、遺言書が作成された後に、不利益な遺言を書かれた相続人によって内容を改ざんされる、あるいは秘匿や破棄されてしまうといった危険性や、そもそも遺言書自体を本人が紛失してしまう可能性がありました。
そこで法律が新設され、令和2年7月10日に法務局での保管サービスが開始しました。
法律が改正されたおかげで、より利用しやすいものとなりました。
【改正内容】
- 財産目録をパソコンで作成、又は通帳の写しなどを別紙添付できる
- 法務局で原本を保管してもらえる
- 法務局に保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要となる
◇公正証書遺言
遺言者が口頭で述べたことを公証人が直接聞いて作成するのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言には、二人以上の証人の立ち会いが必要となり、遺言者の意思を公的な立場で保証してもらえるメリットがあります。
まずは遺産のリスト、不動産の地番や家屋番号などの必要書類などを用意し、公正役場で作成を依頼します。 証人は署名する日に公証役場に行くだけですが、身分証明のための書類を持参すると良いでしょう。
なお本人が公正証書遺言で使用する印鑑は、実印でなければなりません。 相続の専門家に頼んで、遺言書作成をサポートしてもらうことも可能です
また、公正証書遺言の原本は「公証役場」に保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険はありません。費用はかかりますが遺言の方式としては、最も安全で確実といえます。
ただし、作成に関して比較的手間と費用がかかります。
また、公証人と証人が関わることによって、遺言書の内容が完全に秘密になるわけではありません。
公正証書遺言はその効果が無効になってしまうことはありませんが、その他の遺言書と同様、特定の相続人の利益になるような内容でも、効果を発揮してしまうので、遺留分の対策など作成に関して十分な検討が必要となります。
★まとめ
家族のことを思って生前に書き記した遺言書が、単純ミス等のせいで無効となってしまっては、遺言者も家族も報われないことでしょう。また、遺言書が無効になるかならないかといったことが原因で、相続が争族に発展してしまう可能性も否定できません。
今まで仲の良かった兄弟や親族等が相続をきっかけに仲違いしてしまうことを望む遺言者はいないと思います。大切なご家族のためにも、事前にしっかりと検討をして遺言書を作成していただきたいと思います。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。