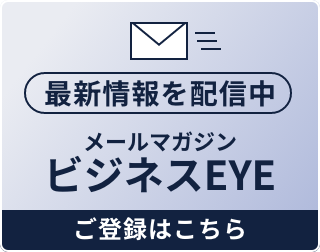お子様がいない場合には財産は誰のもの?
トラブルを未然に防ぐ対策
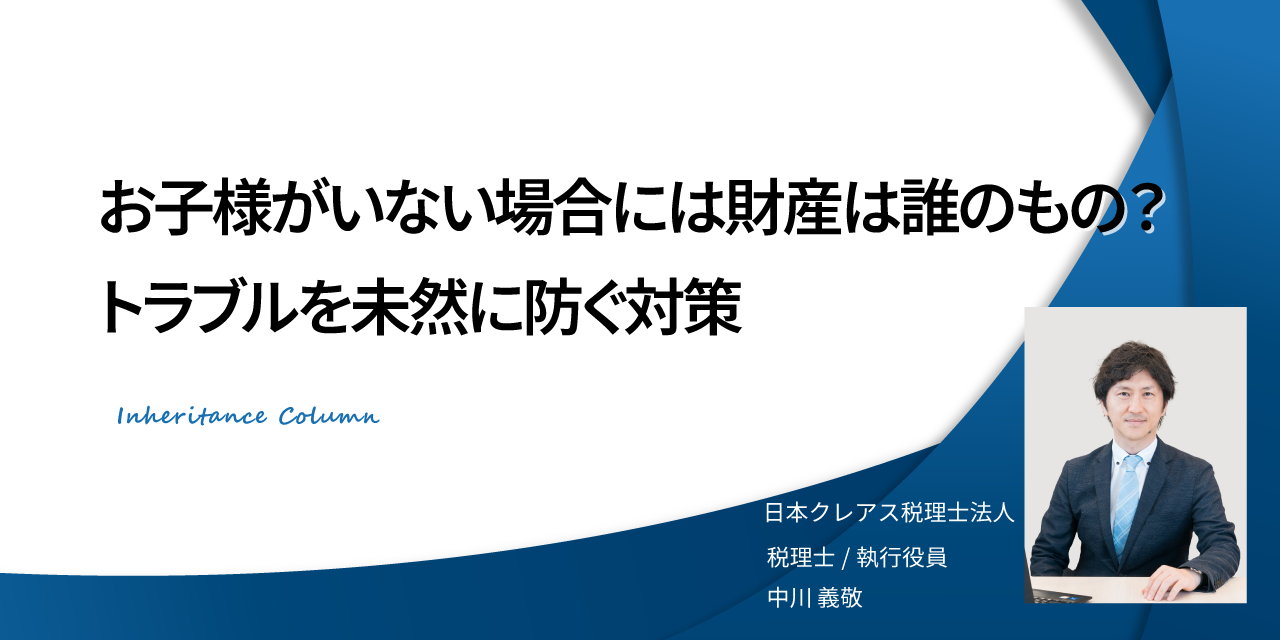
子供がいないご夫婦の一方が亡くなり、相続が発生した場合、普段連絡を取り合っていない親族間で相続に関する遺産分割の話をすることになり、相続トラブルに発展することもあろうかと思います。
法定相続人になる人の範囲と順位は民法で決められていますので、誰が相続人になるのか確認しておくとともに、トラブルにならないように事前にしっかりと対策をしておきたいものです。
そこで今回は、子供のいないご夫婦の相続について、起きやすいトラブルとその対策についてご説明いたします。
■子供がいない夫婦の相続人は誰になる?
相続が起きた場合、誰が相続人になるかは民法で定められていて、その定められた相続人のことを法定相続人といいます。
子どもがいない夫婦でどちらか一方が亡くなった場合には、その配偶者が財産の全てを相続するわけではなく、親や祖父母または兄弟姉妹、姪や甥も相続人になる可能性があるため注意が必要です。
被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外にも相続人になる人がいます。
子供がいない場合、子供の代わりに第二順位の相続人である親や祖父母などの直系尊属、第二順位の相続人がいなければ、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
親や祖父母、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹の子どもである、被相続人の甥や姪が相続人となります。
そして、相続できる親族が誰もいない場合、遺言書がないと、国に全ての財産が帰属されます。
■起こりやすいトラブルとは?
相続で揉める家族の特徴として相続人同士が疎遠であることが挙げられます。
遺産を分けるときは相続人全員で遺産分割協議をする必要があるため、被相続人の配偶者が面識のない被相続人の親戚と遺産分割について話をすることになったり、配偶者にとっては想定していない相続人が急に現れるかもしれません。
遺産分割協議が配偶者の精神的な負担になる可能性がありますし、疎遠な親戚であっても権利分は全て請求する人もいるかもしれません。特に遺産に不動産がある場合は、遺産分割しにくいため、遺産をめぐってトラブルが起きやすくなり、遺産に自宅の土地建物がある場合、配偶者が自宅をすべて相続できない可能性も生じてきます。
■トラブルを回避する事前の対策は?
◇遺言書を作成する
相続が発生すると、相続人全員による遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書により遺産分割方法を指定しておけば、遺言書による指定が優先されるため、遺産分割協議がまとまらずトラブルに発展する可能性を未然に防ぐことが可能です。
ただし、遺留分といって、法定相続人に最低限保障される遺産取得分があるため、一人の相続人に偏った財産分与すると、財産の分配がなかった相続人が遺留分侵害請求することになって、違うトラブルを生み出す可能性があるので、遺留分を侵害しないよう遺言書を作成することをお勧めします。
なお、兄弟姉妹及び甥姪には遺留分はありませんので、親や祖父母が相続する場合に遺留分を考えることが必要になってきます。
◇生前贈与を活用する
生前に贈与した財産は、法定相続分や遺留分から除かれるため、特定の人に早めに財産を渡したい場合には有効です。
また、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、一定の要件を満たせば、居住用建物やその敷地を生前に配偶者に贈与しておくことで、贈与税の計算において特別控除として最大2,000万円の控除を受けることができます。
この贈与の方法を、おしどり贈与と呼ぶこともあります。
生前に持ち家の贈与を受けていれば、遺産分割の際には、贈与した居住用土地建物は相続財産に加えられることなく、残った遺産を法定相続分によって取得することが出来ます。
ただし、生前に一人の相続人が多額の贈与を受けている場合、その贈与分を特別受益の対象財産として相続財産へ加算されたうえで遺産分割をする場合があります。この相続財産へ加算することを特別受益の持ち戻しといいますが、相続人間での協議の際、特別受益の持ち戻しをするかどうかで、特別受益を受けた人と受けていない人で利益が相反し、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
◇生命保険金の契約をする
生命保険金の受取人は保険契約によって定められているため、相続人による遺産分割協議によって受け取る人を変更することはできません。
そのため、財産を渡したい特定の人を保険金の受取人にしていれば、確実に財産を渡すことができます。さらに、生命保険金は法定相続人一人当たり500万円の控除を受けることができるため相続税の節税にもつながります。
◇普段からのコミュニケーションを円滑にする
子供なし夫婦の相続に限らず、普段から相続財産を受け取る親族間同士で財産の詳細や、どのように配分を行うかについて、話し合っておくことによってトラブルを軽減できることもあります。
相続人と疎遠になっていると、話し合いの場面も持ちにくいかもしれませんが、なるべく、遺産分割協議が必要となる前から、相続人同士で良好な人間関係を作っておくことが結果的に相続に関するトラブル防止につながることになります。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。