2025.05.08
相続
超高齢社会にとって当たり前の対策?家族信託のキホン
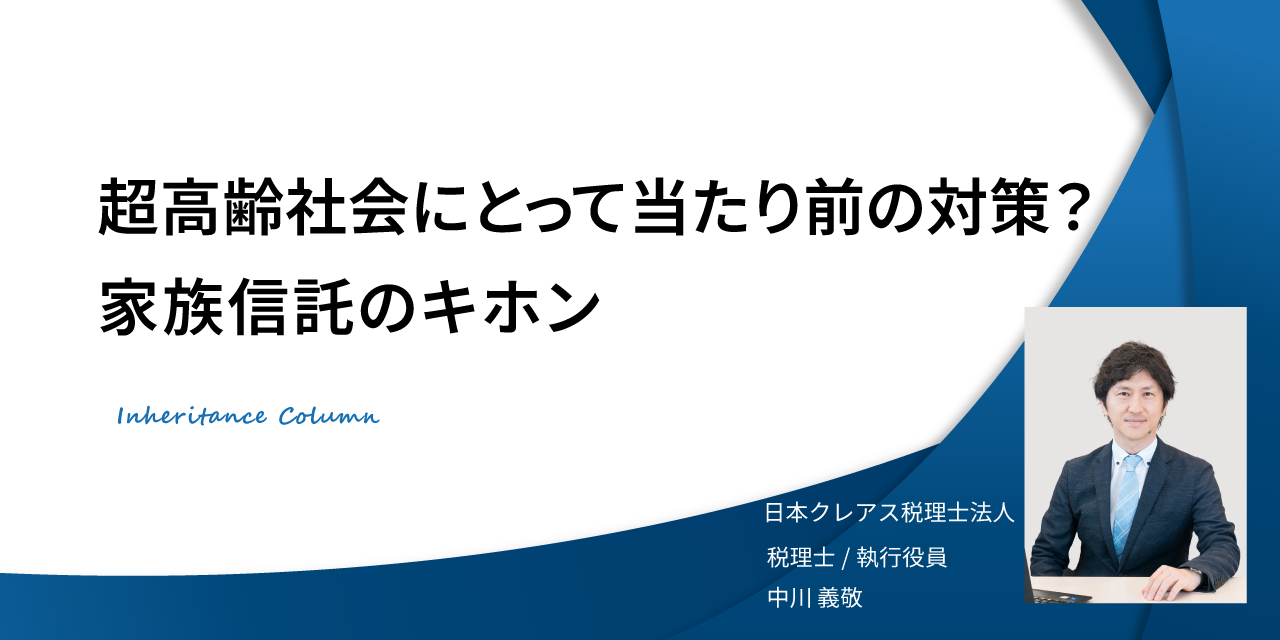
内閣府が公表している情報によりますと、2024年10月時点の65歳以上の人口は3,623万人、総人口に占める65歳以上の人口の割合(高齢化率)は29.1%と、現在も超高齢社会が継続している状況にあります。
また、年齢が上がるにつれて認知症になる確率も上昇していることから、認知症を患っている人も年々増加傾向にあります。
認知症が進行すると、判断能力の低下を理由に銀行の口座などが凍結されてしまうことも考えられます。
そうなると、本来は親族である子どもでも親のお金を下ろすことができないため、ご自身の介護費用を子どもが負担するなどの弊害が発生しかねません。
そのような、将来の認知症のリスクに備えた対策の一つとして、家族が財産の管理等を可能とする「家族信託」という手法が注目されています。
そこで今回は、家族信託の基本と具体的に有効となるケースついてご説明いたします。
■家族信託とは?
家族信託とは、家族によって財産の管理、運用、処分ができる一つの手法です。
家族信託には、
「委託者」(財産について信託する人)、
「受託者」(信託財産の管理・運用・処分等を行う人)、
「受益者」(財産から利益を受ける人)が登場します。
認知症などにより判断能力が低下し自分で財産を管理できなくなることへの備えとして、注目されています。
「委託者」と「受益者」は財産を所有している親、「受託者」は子どもといったイメージで、例えば、財産の所有者である親(委託者)が認知症により財産を管理できなくなってしまった場合でも、信託した財産に限り、子ども(受託者)が財産の管理、運用、処分をすることができるようになり、財産の運用や処分によって得た金銭は財産を所有する親(受益者)が受けることができます。
■家族信託が必要な場合とは?
では、家族信託が有効になるケースとは、どのような場合が考えられるのか具体的に見ていきましょう。
1)親の介護費用、生活費、医療費を親の財産から支払う場合
医療費や介護費用、老人ホーム入居費などを親の財産から支払いたい場合は、認知症などを理由にご本人が支払いをすることが困難になった場合には、家族信託を活用すれば奥様やお子様が受託者となることで財産を管理、運用することが可能となり、諸々の支払い行為をすることが出来ます。
2)不動産などの財産を所有及び不動産収益を得ている場合
アパートなどの収益物件がある場合、認知症などにより所有者が財産管理することが難しくなったとしても、家族信託によりお子様などが継続して財産管理を続けられるようになります。
なお、不動産会社に管理を任せていたとしても、修繕工事や賃料の不払いへの対応、物件の売却などの場面で支障が生じる場合があるため、家族信託をしていれば安心です。
3)家族のみで財産管理を行うようにしておきたい場合
本人以外が財産を管理する手段として成年後見制度もありますが、家族以外の専門職が選任されたり、監督人が選任されたりするので、家族以外の第三者の意思が入ってしまうことに不安がある方や専門職の報酬負担が気になる方は家族信託を検討してみてもよいかもしれません。
4)二次相続まで、財産の承継先を決めておきたい場合
家族信託では、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」にすると先々の相続のことまで決めておくことができます。例えば、今の所有者が亡くなったら、配偶者が相続し、配偶者がなくなったら長女が相続するというようなことを決めておくことができます。遺言書ではこれを実現することはできませんが、家族信託では対応が可能です。
5)財産管理が困難な子どもに財産を残したい場合
何らかの要因により財産の管理が難しい子どもがいる場合、将来の生活保障に家族信託を利用することによって、親が委託者、子どもを受益者とし、信用のおける親族などを受託者にすることで、子どもに対して適切な財産管理や運用または処分を行うことも可能となります。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。








