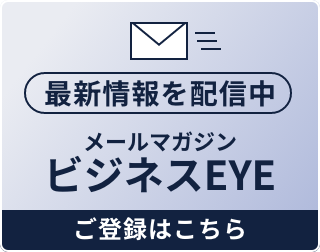路線価って何に使うの?
相続における不動産の評価方法について
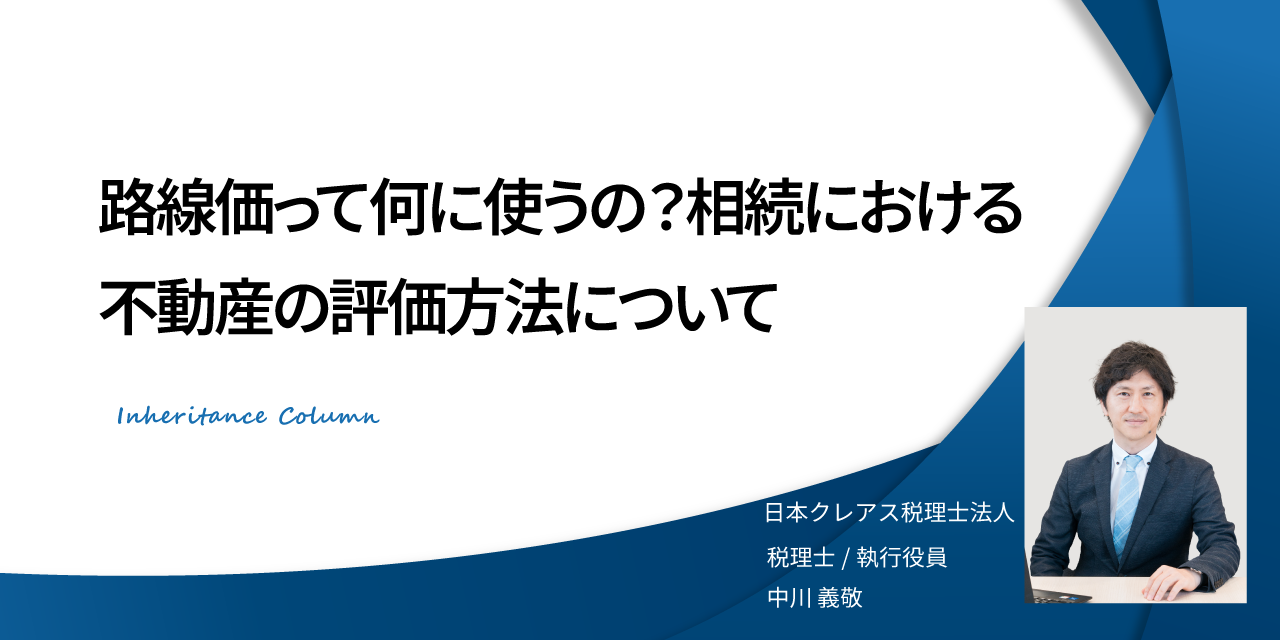
令和7年7月1日に、国税庁から令和7年分の路線価が発表されました。
全国の平均変動率は前年比2・7%増と4年連続で上昇している状況で、平成22年以降で最大の伸び幅となっているようです。東京や沖縄、福岡など都心や観光により需要が高い都市部は地価が上昇していますが、新潟や山梨、奈良といった地方の一部では下落傾向が続いている模様です。
路線価は、相続や贈与により土地の評価を計算するうえで必要となる指標で、相続対策を検討される方、実際に相続や贈与が発生して土地の権利が動く場合には、必ず確認が必要となります。相続対策に関して、不動産は相続財産の中でも大きな金額を占めるため、生前に評価額を把握しておくことは非常に重要です。
そこで今回は、路線価の概要と不動産評価の関係性についてご説明いたします。
■そもそも路線価とは?
路線価とは道路に面している土地の1㎡あたりの評価額をいい、国税庁のホームページに公表されている路線価図により調べることができます。土地の形状がいびつで利用勝手が悪い土地や、道路に面する土地の間口が狭い土地は、建物の配置が制限されることになるので、きれいな正方形や長方形の形状をした土地に比較して減額されることとなります。
■不動産の評価額とは?
不動産の売却や購入を検討する場合、もしくはご家族に相続があった場合、不動産の評価額を目安に、これらの金額の根拠とすることができます。
不動産を評価する場合、売却や購入、相続時点の「時価」をもって評価額とするのですが、何をもって時価=評価額と考えるのか、その基準を明確にする必要があります。
■不動産評価額の種類と調べ方
不動産の評価額は、原則的に「固定資産税評価額」「相続税評価額」「公示価格」の3種類あり、目的に応じてこれらの評価額のうち、いずれかを用いることになります。
相続税評価額は相続税や贈与税を算出する際に用いる評価額をいいます。不動産の所在地によって、路線価方式と倍率方式の2つ計算方法があります。
1.路線価方式
路線価方式により評価額を計算する場合には、下記の算式により算出します。
評価額=路線価×地積×調整率
2.倍率方式
路線価図により路線価が付されていない地域については「固定資産税評価額×倍率」により評価額を算出します。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準となる価格をいい、毎年4月から6月頃に自治体から届く「固定資産税納税通知書」に記載されています。なお、倍率は国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表により確認することができます。
■不動産評価額と売却価格との関係は?
「固定資産税評価額」と「相続税評価額」は自力で算出することができる不動産評価額となります。ここでは、「固定資産税評価額」「相続税評価額」が実際の売却価額とどのような関係性にあるのかについてご説明いたします。
固定資産税評価額と売却価格との関係
固定資産税評価額は各市区町村が算定するのですが、公示価格の70%の水準になるように調整されていますので、固定資産税評価額を0.7により割戻すことにより、公示価格を把握することができます。
公示価格は国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公表する不動産価格の事で、固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)の基準となります。公示価格は毎年公表されるので不動産価格の現在の水準を推測することに用いることができます。
ただし実際の不動産の取引価格は土地の形状や道路幅、その他個別事情によって大きく変化しますので、公示価格はあくまで不動産相場を知る1つ参考指標として用いることとなります。
公示価格と売却価格の関係は地域によって異なるのですが、売却価格はおおよそ公示価格の1.1倍から1.2倍と言われているので、固定資産税評価額は売却価格の0.6倍から0.65倍を目安に考えることができます。
相続税評価額と売却価格との関係
相続税評価額は路線価に基づき算出されるのですが、路線価は公示価格を参考に国税庁によって評価が行われ、公示価格の80%の水準になるように調整されています。
相続税評価額を0.8により割戻すことによって公示価格を掴むことができます。ただし相続申告や贈与申告においては路線価のみならず、土地の形状や大きさ、道路幅などを鑑み、相続税法独自のルールにより一定割合減額して評価を行います。
一概には言えませんが、相続税評価額は売却価格のおおよそ0.7倍から0.75倍を目安に考えることができます。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。