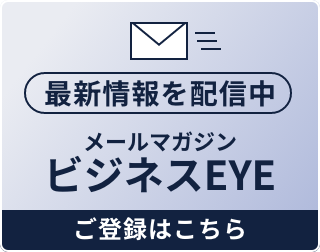小規模宅地等の特例で賢く節税!
「家なき子特例」について徹底解説!
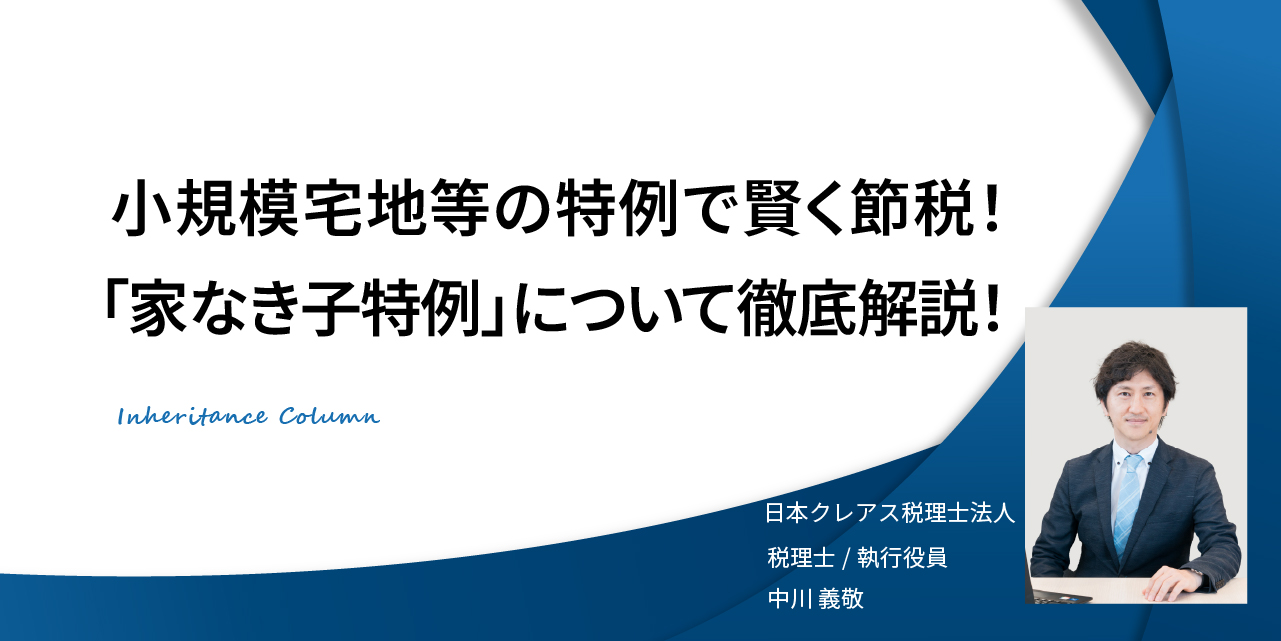
「別居親族による実家相続の問題」は、相続を巡る諸問題の中でも、重要なテーマの代表格と言えます。
お亡くなりになった方の自宅に対する「小規模宅地等の特例」は、本来なら同居する相続人しか適用できません。
ただし、持ち家がなく一定の要件を満たした相続人に関しては、例外的に「家なき子特例」による評価減が認められています。
小規模宅地等の特例を使えるかどうかは、相続税の節税対策を検討するうえで外せない内容なので、家なき子特例とともに、適用要件をしっかり押さえる必要があります。
今回は小規模宅地等の特例の概要とともに、家なき子特例の条件についてもご説明いたします。
■そもそも「小規模宅地等の特例」とは?
小規模宅地等の特例とは、相続した土地の課税価格を50%または80%減額できる税制上の特例で、相続対策を検討する上で、必ず利用したい特例のひとつです。
なお、小規模宅地等の特例の対象となる土地には3種類存在します。
【対象となる土地】
- 特定居住用宅地…所有者やその親族の居住に使われている土地
- 特定事業用宅地…第三者(個人や一定の法人)に貸し付けられている土地
- 貸付事業用宅地…その他、事業用に使っていた土地
今回は、上記3種類のうち自宅として利用する「特定居住用宅地」について解説します。
■「家なき子特例」とは?
家なき子特例の特徴は、被相続人と別居していても「直近で持ち家に住めていない」相続人には、例外的に小規模宅地等の特例の適用が認められるということです。
制度上の仕組みには正式な名称がないものの、適用要件に合致する持ち家を持っていない相続人について、要件そのものを「家なき子特例」と税務上呼称します。
本来、配偶者以外の相続人が、特定居住用宅地として、亡くなった人の住まいを相続しようとする場合、被相続人と同居していた「相続人の居住要件」を満たさなければなりません。
つまり、これから相続する家の評価減を認めてもらう前提として、現に相続人自身が対象不動産に住んでいなければならないのです。
もともと同居していたという要件を厳格に運用することで不利益を受けるのは、
「仕事や学業の都合で一時的に別居する人」や「経済等の理由で当面は住宅購入できない(する予定がない)人」です。
このような人が実家を相続する際に重税を課せば、せっかく自分のものになった家は売却せざるを得なくなり、結果として帰る家を失ってしまうかもしれません。
このような不利益をなくすため、被相続人と別居していても持ち家に住んでいない相続人には、小規模宅地等の特例を認めましょうという例外規定が存在するのです。
■家なき子特例の要件
居住用宅地の相続人は、(1)被相続人、(2)土地建物、(3)相続人の3つの要件を全て満たしたときに「家なき子」とみなされます。
【要件1】被相続人(=亡くなった人)の要件
配偶者がいない(未婚or死別のどちらの理由でも可)
【要件2】土地建物の要件
- 亡くなるまで被相続人の居住の用に供されていた
- 相続開始の直前に、その土地建物に居住していた相続人がいない
- 相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月目)まで相続人名義で所有されている
【要件3】相続人の要件
相続開始前3年以内において以下①~④のいずれにも居住したことがなく、かつ相続開始時点で居住している土地建物を過去に所有したことがない
- 自己名義の持ち家
- 自己の配偶者名義の持ち家
- 自己の三親等以内の親族名義の持ち家
- 自己と特別の関係がある一定の法人所有の家屋
■家なき子特例での相続対策
現状の家なき子特例は、「相続人に当面のあいだ賃貸暮らしを継続する予定がある」ことが活用の前提になります。生前対策の段階で特例の活用を検討できる例は、以下のようなものが典型的です。
- 勤務地で貯蓄しながら賃貸暮らしを続ける子に、将来は実家を売却するなどして生活設計に役立ててほしい。売却代金を出来るだけ手元に残せるよう、税負担を軽くしておきたい。
- 孫が大都市所在の大学に進学して寮に移り、そのまま現地で就職する計画を立てている。これを機に将来を見据え、養子縁組や小規模宅地等の特例の適用を駆使して、実家相続の税負担を軽くしておきたい。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。