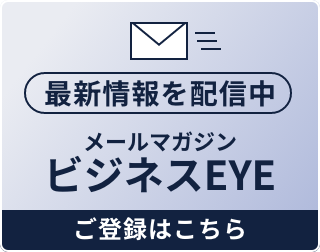自分も後見人をつけた方がいい?
~任意後見制度の利用について~
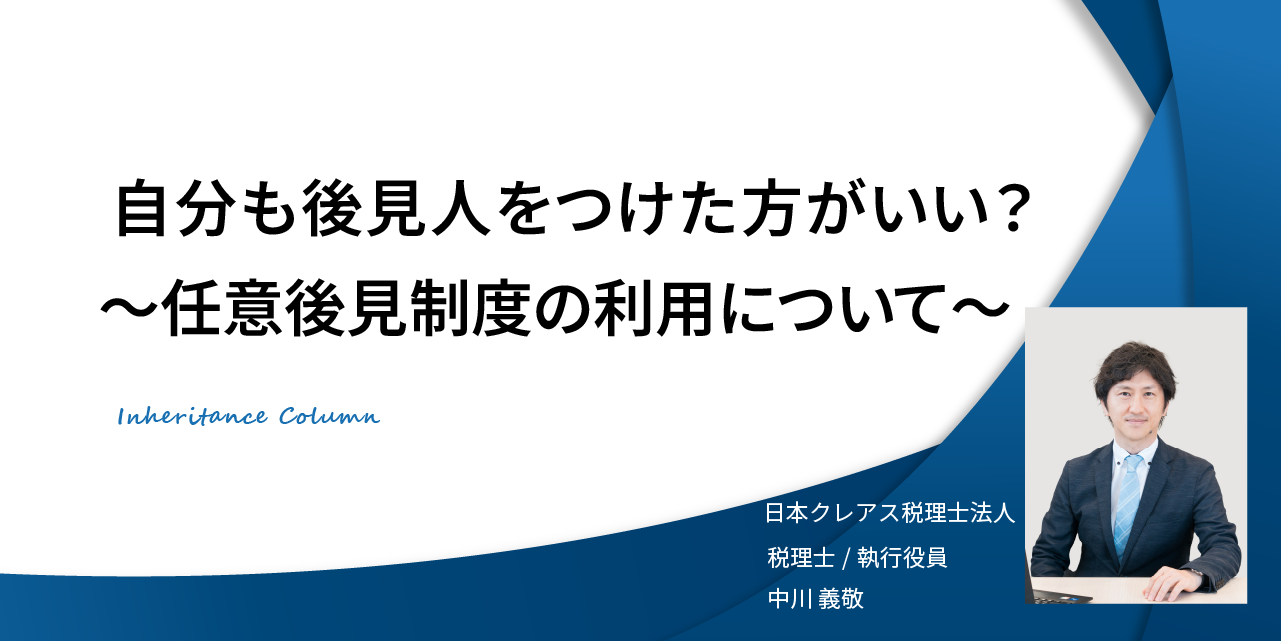
老齢や病で判断能力が落ちてきた人に必要なのは、日常生活のサポートだけではありません。
その財産管理が適切に行えるよう「成年後見制度」というものがございます。
成年後見制度は「法定後見制度(法定後見人)」と「任意後見契約(任意後見人)」の2つに分かれていて、後見人の種類もさらに細分化されており、本人が必要とするサポート範囲に合わせて決めることが出来ます。
成年後見人に関するルールは法律でしっかり定められていますが、ご本人(=被後見人)の意思を最大限尊重できるとも限りません。「任意後見制度」は、比較的ご本人の意思を通しやすいですが、任意後見人がつくと生活がどう変わるのか、どのように手続きすればいいのか、とお悩みの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は任意後見制度の仕組みや手続き方法についてご説明いたします。
■成年後見人とは?
まず成年後見人とは、認知症・知的障害・老齢による判断能力の低下などがみられる人について、その財産管理の権限が与えられた人物を指します。
法令や家庭裁判所が定める「成年後見制度」のルールに沿って選ばれ、本人の代わりに金銭の契約や管理(財産行為)を判断・実行します。
成年後見制度は「法定後見制度(法定後見人)」と「任意後見契約(任意後見人)」の2つに分かれています。
【成年後見人による財産行為の一例】
- 銀行口座からの出金
- 居住用不動産のメンテナンス
- 携帯電話等のライフラインの新規契約
- 本人が居住する賃貸アパートの更新契約
- 遺産分割協議への参加(制限あり)
■成年後見人に出来ること・出来ないこと
成年後見人としてサポートを開始する際は、本人の心身の安全に配慮する義務(身上配慮義務)・本人の意思を最大限尊重する義務(意思尊重義務)に従わなければなりません。
その上で、成年後見人に認められる権限は「身分行為を除く財産の管理・処分」に限られています。
■任意後見契約とは?
任意後見契約とは、まだ判断能力が衰えないうちに後見内容を契約として結んでおき、後見が必要となったタイミングで発効するものです。
法定後見制度では得られない最大のメリットは「後見人を誰にするか」、「代理権の範囲はどうするか」といった条件を細かく本人が決められる点です。
医師の診断さえあれば家裁の判断を待たずとも、すぐに後見内容が実現されるため、本人・家族ともに不安定な立場に置かれにくいというメリットもあります。
判断能力はすぐに失われるものではなく、徐々に低下していくものです。
現実問題として、本人とその家族は「いつ後見が必要になるかはっきりと分からない」という点に悩まされるでしょう。
任意後見契約では、本人がすぐ必要とする支援・いずれ判断能力が落ちた時に必要とする支援に切り分けた上で、後見とは別の契約としてそれぞれ結んでおくことが出来るため、段階的に支援体制を整えることが出来るのです。
【利用イメージ】
- 判断能力が低下する前
…任意後見契約と同時に、日常生活を支援するための「見守り契約」を結ぶ - 判断能力が少し低下してきたとき
…財産の管理処分を任意後見人予定者に任せるための「財産信託」を結ぶ - 判断能力が明らかに低下したとき
…任意後見契約を発効させ、別の家族からの相続や死後事務に備える
■任意後見監督人が必ずつく
任意後見契約が発効したときは、その業務が適正に行われるよう「任意後見監督人」が必ず選任されます。任意後見人には財産目録作成と定期報告義務が課せられるため、不正の心配もありません。
以上のことから、任意後見制度はより使い勝手のよい「終活の一環」として利用できます。
■任意後見人の申し立て手続きの流れと方法
任意後見契約を行う際は、本人と将来後見人になる人との間で「公正証書」により支援内容を取り決めます。発効させたいときは、判断能力低下を証する書面を添付し、家裁で手続きしなければなりません。
公正証書を作成する前に、以下の各事項について取り決めを行います。
後見内容についてすべて取り決めが終わると、本人と後見人予定者が揃って公証役場に向かい、公証人との面談を経て公正証書作成を行います。
【後見人契約時に取り決めるべき事項】
- 契約の趣旨
- 契約の発効時期
- 後見人の義務・業務範囲
- 任意後見人への報酬
- 契約の解除規定
- 契約の終了規定
■契約の発効手続き(後見開始)
判断能力が低下したときは、後見開始・監督人選任を同時に行う「任意後見監督人選任審判の申立」が必要です。下記のように、契約の当事者もしくは家族が申立人になることが出来ます。
<任意後見監督人選任審判の申立ができる人>
- 本人(後見される人)
- 後見人予定者(契約を結んだ人)
- 配偶者・四親等内の親族
■監督人候補者の条件
発効の際は、任意後見監督人(任意後見人の活動をチェックする人物)の候補者を立てることが認められます。監督人候補者に特別な資格は不要ですが、本人・任意後見人の双方と利害関係にないことが求められます。
遠縁の親類に候補者になってくれる人がいない場合は、心当たりがない場合は弁護士・司法書士などに依頼しましょう。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。