2025.09.09
相続
人生100年時代を生き抜く!大切な年金の受給と増額方法
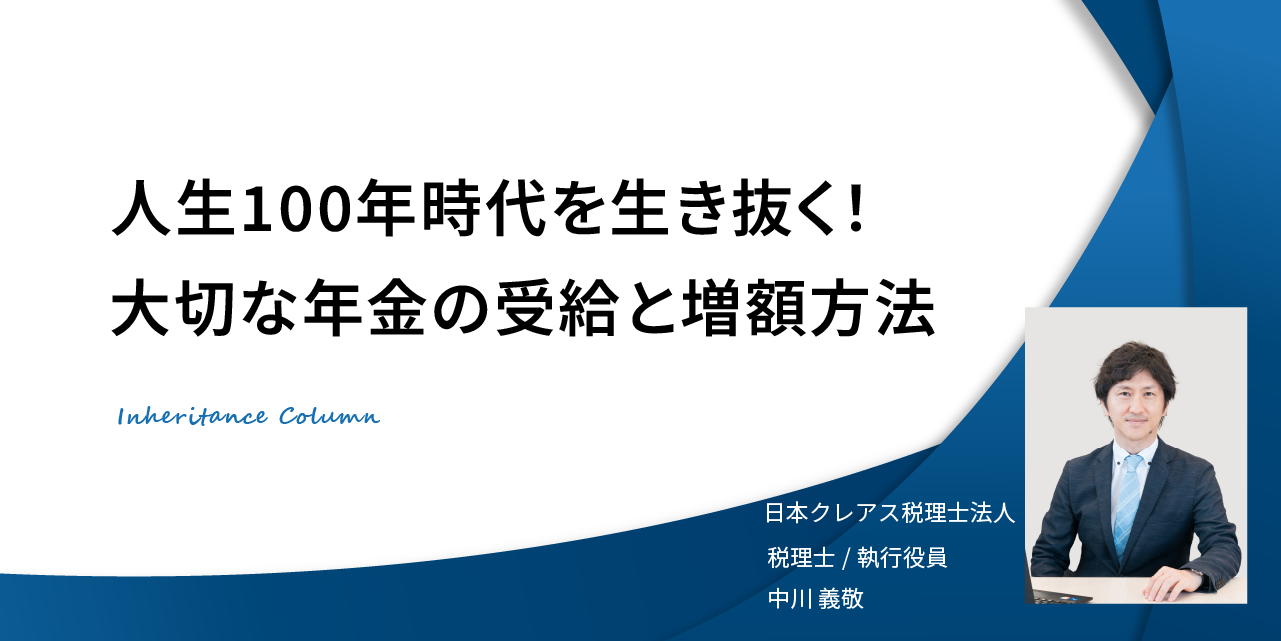
国民年金・厚生年金の受給開始は原則65歳からですが、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。そのため、どの年齢で受給開始するのか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、厚生年金と国民年金の基本的な内容と年金受給額の増額方法ついてご説明いたします。
厚生年金とは?
厚生年金は、会社員や公務員の方などが加入する年金です。一般的に、国民年金の第2号被保険者に該当します。届出方法は、お勤め先を通じて事業主が届出します。
保険料の納付方法に関しても、お勤め先を通じて納付します(給料から天引きされます)。
保険料は月ごとの給料に対して定率となっていて、実際に納付する額は人によって異なります。また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額となります。
厚生年金と国民年金の違いは?
国民年金は、農業者・自営業者・学生・無職の方などが加入する年金で、一般的に国民年金の第1号被保険者に該当します。届出方法は、ご自身でお住まいの市(区)役所または町村役場へ届出します。保険料の納付方法は、納付書による納付や口座振替など、自分で納めます(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります)。
保険料の金額は17,510円(令和7年度)のほかに、月額400円の付加保険料を納付することによって、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度もあります。
一方で、厚生年金に加入している方は、国民年金の第2号被保険者に該当し、第2号被保険者は国民年金と厚生年金の両方に加入しているため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れます。
厚生年金や国民年金などを受給していた人が、死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
また、死亡したときに支給されていなかった年金を、遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
厚生年金の計算方法は?
国民年金に加入している方は、40年間払えば満額となるため、老齢基礎年金の満額を受け取ることが可能です。しかし、厚生年金の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金とに分かれています。この老齢厚生年金部分には満額という概念がありません。
そのため、老齢厚生年金は、年収と加入期間に応じて受給額が決まるので、納めた金額が多いほど貰える年金額も増えることになります。
令和3年度の厚生労働省年金局の資料によると、国民年金の老齢年金受給者の平均的な年金の月額は、56,479円に対し、厚生年金の老齢年金受給者の平均的な年金の月額は145,665円となっております。このデータから厚生年金の受給者は国民年金の受給者の2.5倍以上になっており、厚生年金の加入の有無によって年金に差が出ることがわかります。
厚生年金の計算シミュレーション
具体的な年収ごとの厚生年金の受給額に関しては、下記をご参考にしてください。
①年収500万円で40年間年間保険料を納付した場合
65歳から受給すると年間約180万円の年金が貰えますが、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、約260万円まで増加します。
②年収700万円で40年間年間保険料を納付した場合
65歳から受給すると年間約220万円の年金が貰えますが、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、約320万円まで増加します。
(※)上記年収は23歳から63歳まで働いた場合の平均年収と仮定。
厚生労働省の令和4年簡易生命表によると、日本人男性の平均寿命は81.05年、女性は87.09年となっており、このデータによると65歳から受給を開始した年金金額と70歳から受給を開始した年金金額とでは、男性の場合においては、そこまで差が無いことがわかりま
厚生年金の受給額を増やすには?
上述しました通り、国民年金と比較した場合、厚生年金の方が将来貰える金額が多いのがわかるかと思います。しかし、仮に年収500万円だとしても貰える年金は年間約180万円となるため、将来貰える年金額を増やしたい方もいるかと思います。
増やす方法としては、勤務されている会社が確定給付企業年金もしくは企業版型確定拠出年金を実施しているのであれば、加入をすることにより年金の金額を確実に増やすことが可能です。逆に会社が実施していない場合には、iDecoに加入することにより増やすことが出来ます。
2022年10月以降、法改正に伴い国民年金被保険者であれば、誰でも加入できるため、厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者に該当するため加入することが可能です。
あとは、民間の保険会社等が実施している個人年金等に加入することにより増やすことが可能ですが、こちらの場合リスクがある商品もありますので、その点は保険会社等の説明をキチンと受けたうえで、加入することをお勧めします。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。是非お気軽にお問合せください。








