2025.09.22
相続
そんなにハードルは高くない?養子縁組の手続き方法
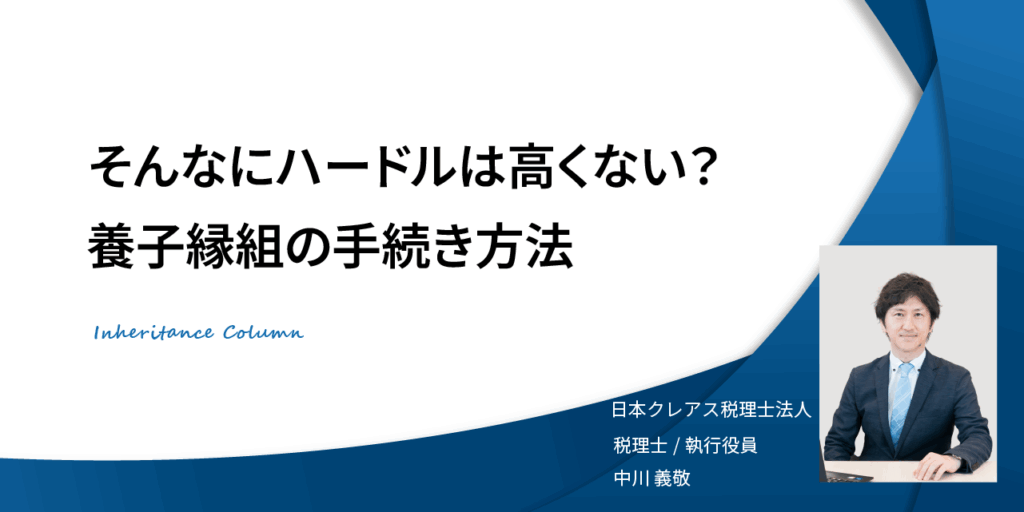
再婚により前の配偶者との間に生まれたお子様がいる場合、婚姻届を出しただけでは、その子どもとの親子関係は成立せず、
自分に相続が発生した場合、その子どもには相続権がありません。
そのままにしておくと、もし再婚相手との間に子供が生まれた場合、結婚後に生まれた子には相続権があるのに、連れ子にはないという状況になります。
その他にも、お孫さんに直接相続財産を渡したいと思っても、遺言書を作成しないと財産を受け取る権利が発生しないなど、
法定相続人でない場合には、財産を受け取ることが出来ません。
このようなお悩みを解決するために、「養子縁組」という制度がございます。
そこで今回は、養子縁組の概要・注意点、その手続き方法についてご説明いたします。
養子縁組とは?
まず養子縁組とは、法律上の親子関係を作る手続きのことを指します。
養子縁組をした子は、法律上実子と同じ扱いとなって、法定相続人の1人としてカウントされます。
相続における養子縁組といえば、相続税の基礎控除額(※)を増額させるための節税策としてよく知られる方法です。
※基礎控除:相続財産の総額から控除することが出来る一定の金額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、新しい夫婦の戸籍に連れ子を入れるには、いくつか方法がありますが、連れ子を戸籍に入れた上で法定相続人にするためには養子縁組が必要です。
養子縁組をすることで、連れ子は法律上の子供となり、相続権も発生します。
連れ子を戸籍に入れるだけなら入籍届という手続きもありますが、この手続きでは親子関係は生まれず、連れ子に相続権はありません。
つまり戸籍が同じであることが相続人の条件なのではなく、法律上の親子関係がある(その結果、戸籍に入る)ことが相続人の条件なのです。
養子縁組の方法は?
養子縁組を行うには、市区町村役場に「養子縁組届」を必要書類とともに提出して行います。
必要書類は、下記の資料が必要となることが一般的ですが、届け出を行う市区町村役場のホームページなどで事前に確認したほうがいいでしょう。
- 各人の戸籍謄本
- 本人確認書類
- 配偶者(結婚相手)の同意書
「養子縁組届」は、養親(新しい親)になる人と養子になる子で提出します。
養子となる子の年齢が15歳未満のときは、法定代理人(親権者など)が養子縁組の承諾が必要ですが、
15歳以上であれば、本人の意思で養子縁組の承諾を行うことができます。
特別養子縁組について
子どもの年齢によっては「特別養子縁組」という方法もあります。
子どもが原則15歳未満のときに、家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。
「特別養子縁組」では、通常の養子縁組と異なり、別れた実の親との親子関係が消滅します。
相続権に関して言えば、通常の養子縁組では、新しい親と実の親の両方から、子供は財産を相続する権利がありますが、
特別養子縁組では、別れた実の親から相続する権利はなくなるということです。
そのため、例外はありますが、原則として子供の実父母の同意が必要となります。
養子縁組せずに財産を残す方法は?
血の繋がりのない子供を法律上の相続人とするには、養子縁組が必要です。
では法律上の相続人にしなければ絶対に財産を遺せないかというと、それは違います。
法律上の相続権がない人に財産を遺すことができる「遺贈(いぞう)」という制度があるからです。
遺贈とは
遺贈とは、遺言書によって、財産を特定の人に遺すことです。
遺贈の相手は、法律上の相続権がなくてもよいため、この方法であれば、相続権のない人を財産の受取人に指定することができます。
この方法は、生前のうちに一定のルールに沿った遺言書を作成しなければなりません。
ただし、他の相続人がもつ遺留分という権利を侵害する遺言書を作成すると、争いのもとになるので注意が必要です。
相続税の2割加算による相続税の負担に注意
遺贈によって得た財産にも、相続税が課税され、このときの「2割加算」のルールに注意が必要です。
2割加算のルールとは、配偶者や子(養子を含む)などの法定相続人以外の人が相続や遺贈によって財産を得ると、その人が支払う相続税は、通常より2割加算されてしまうというものです。
もし養子縁組をせず、遺贈によって財産を遺した場合、その財産を受け取った人には2割加算のルールが適用されるため、養子縁組をして同額の財産を相続したときよりも、相続税の負担が重くなるということです。
再婚した親と連れ子の相続は?
離婚や再婚が相続に関係してくるのは、血の繋がりのない者同士の話です。
連れ子の親(子供の実の親)は、仮に再婚を繰り返したとしても、子供との親子関係は消滅せず、相続権もなくなりません。
そもそも法律上の相続権をもつ人は、配偶者と一定の血族関係にある人です。
血族関係は、離婚や再婚ではなくなりませんので、親が再婚して戸籍や名字が変わったとしても、子供は親から相続を受けることが出来ます。
つまり連れ子は、別れた実の親(例:結婚相手の前夫など)からの相続権をもっていることになるため、養子縁組をしなくても相続権を持つことになるのです。
Contact us
お気軽にお問合せ下さい
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。
是非お気軽にお問合せください。








