2025.10.15
相続
似ているようでまったく違う??
~「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い~
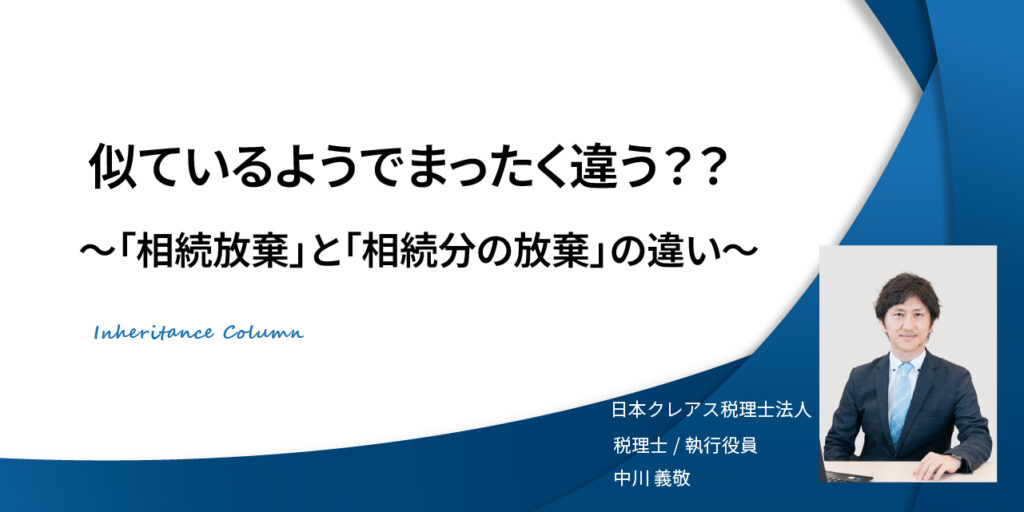
相続が発生した時、相続人はその相続を受けるか(単純承認)、限定的に受けるか(限定承認)、それとも「相続放棄」をするかを選択することになります。
そもそも相続は、原則的には被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することとされています。
権利と義務ということは、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払料金といったマイナスの財産も承継することになります。
もし相続が発生した場合、借金などのマイナスの財産ばかりであれば、その財産は放棄をした方が良いと考える方が多いと思います。
ただ、相続放棄は一定の期限があるため、その期日を経過してしまうと利用することができません。
その場合には「相続分の放棄」というものがあり、放棄という点で言葉は似ていますが、手続き方法などが異なります。
そこで今回は、相続放棄の概要と相続分の放棄の違いについてご説明いたします。
相続放棄について
相続放棄とは、相続権を自ら放棄する手続きのことで、相続財産に関してマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多い場合、プラスの財産だけでは支払うことができませんので、相続人の固有の財産からの支払いが必要になります。
マイナスの財産が、たとえ数千万円、数億円であっても、相続することを承認すれば、無制限に負債を抱えることになります。
このように、相続することでかえって損をするような場合、相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、プラスの財産を得ることはできませんが、マイナスの財産も一切承継することはないため、被相続人の債権者らに弁済する必要がなくなります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うことで手続きが可能です。
相続放棄の申述人になれるのは相続人で、相続放棄をしたい相続人は、各人で、家庭裁判所に必要書類を提出して、相続放棄の申述を行います。
必要書類を提出するまでの流れは下記のようになっています。
1.必要書類の収集
2.相続放棄の申述書を記載
3.家庭裁判所への確認(費用・提出方法)
4.必要書類の提出
申述先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から、原則3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、この期間内に相続財産の調査をしても相続放棄を行うべきか判断できない場合は、家庭裁判所に、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
その場合、伸長されるかどうかは裁判所の判断となります。
いずれにしても、3ヶ月以内に相続放棄の申述を行うことが原則となります。
相続分の放棄とは
一方、「相続分の放棄」とは、相続放棄の手続きをとらず、自らの意思で、遺産の相続を辞退することです。
相続放棄の手続きには間に合わなかったけれど、遺産をもらいたい気持ちがないため、遺産分割協議への参加を辞退するといったケースが該当します。
相続分の放棄が行われた場合、他の相続人は、放棄された相続分を、残された相続人の相続分の比率に応じて分けることになります。
たとえば、配偶者が2分の1、長男と次男が4分の1ずつの相続分のケースで、次男が相続分の放棄をした場合、配偶者の相続分は3分の2(※1)、長男の相続分は3分の1(※2)となります。
(※1)1/2(元の相続分)+1/4(放棄された相続分)×2/3(配偶者の相続分の比率)=2/3
(※2)1/4(元の相続分)+1/4(放棄された相続分)×1/3(長男の相続分の比率)=1/3
相続放棄と相続分の放棄の違い
相続分の放棄は、財産を相続しないという結果を見ると相続放棄と似ているため、事実上の相続放棄と呼ばれることがあります。
しかし、相続分の放棄で辞退できるのは、プラスの財産だけで、マイナスの財産を放棄することにはなりません。
そのため、被相続人の債権者から借金の返済等を求められた時は、相続人としてその請求に応じる必要があります。
「相続放棄」であれば、初めから相続人ではなかったことになりますが、「相続分の放棄」では、法律上の相続人のままということです。
相続放棄と相続分の放棄のどちらを選択したほうが良いのかは、相続の状況に応じて異なるため、早い段階で専門家にご相談することをおすすめいたします。








