2025.09.17
会計・税務
これだけは抑えておきたい!年収の壁(103万円問題)
令和7年税制改正で160万円に!
対象者・企業への影響は? わかりやすく要点のみ解説
目次
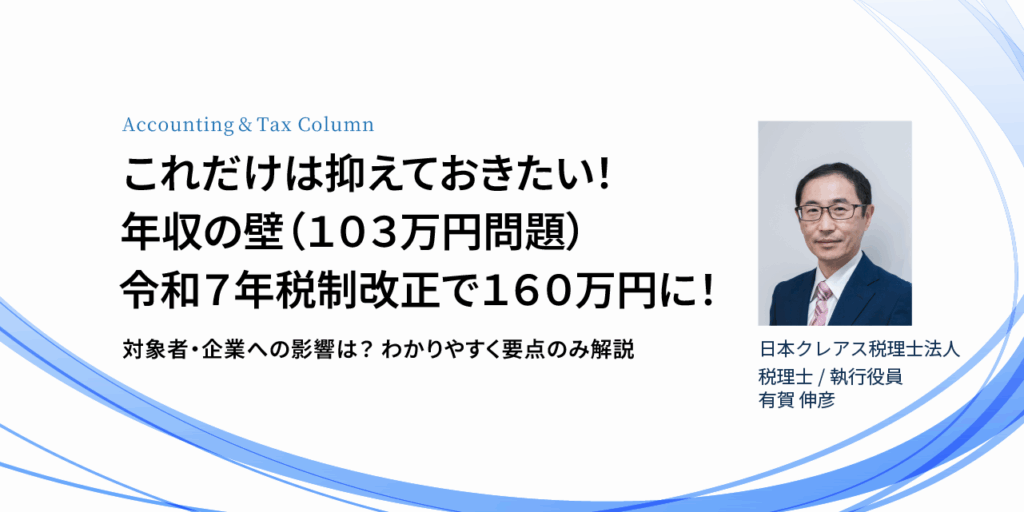
Introduction
はじめに
令和7年度税制改正では
①基礎控除の引き上げ
②給与所得控除の引き上げ
③配偶者の年収要件引き上げ
④扶養控除の年収要件引き上げ
これらの引き上げ改正が行われました。
この中でも特にキーワードとしてよく耳にするのが「103万円が160万円に上昇」という言葉かと思います。
税制に身近に接する私たちは当然ですが、なんとなく耳にはしているものの実際にどういうことなのかをしっかり把握されていない方も多いのではないかと思います。
今回は、ニュースとして頻繁に取り上げられていた年収の壁(年収103万円問題)を改めてかみ砕いて解説すると共に、それが与える対象者や、企業への影響についても考えてみたいと思います。
●そもそもどうして改正されたのか
パート、アルバイトに従事する不要に入っている主婦や学生などが、一定の年収を超えると税や社会保険料が発生することを負担に感じ、もっと働けるのに働かないという問題を解消するため、というのが主な改正の理由です。
●基礎控除・給与所得控除の引き上げ→所得税課税ラインの引き上げ
まずは、今回引き上げられた「課税所得をゼロにできる」ラインについて見ていきましょう。
これまで、所得税がかかる壁として103万円が下限として設定されていました。
これの内訳をみると基礎控除(給与を取得するすべての納税者が受けられる控除)が48万円、 給与所得控除(経費の代替としての控除)が55万円、併せて103万円となっております。
この控除額が、基礎控除95万円、給与所得控除65万円まで引き上げられ、これまで103万円を超えると課税されていたものが、令和7年以降は160万円までは課税されないことになりました。
つまり、これまで以上に働いても所得税がかからなくなった。
と言うことになります。
なお、160万円を超える場合は、年収金額に応じて基礎控除額は段階的に減少するように設定されています。
改正前は一律48万円の設定でしたが、改正後は95万円~58万円までが設定されています。
●配偶者控除が改正、扶養者の年収上限額が123万円に
次に、パートで働く妻を扶養する世帯の税負担を軽減する制度「配偶者控除」が改正され103万円だった年収上限が123万円まで引き上げられました。
これまでは年収103万円以下(所得48万円以下)である必要がありましたが、これが引き上げられ年収123万円以下、所得58万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。
(本人年収1095万以下、所得900万円以下の場合)
さらに、123万円以上は配偶者特別控除として、160万円までは同じく38万円の控除が受けられます。
●「特定親族特別控除」が創設、19~22歳までの子供がいる親の負担を軽減
さらに、「特定親族特別控除」が新たな制度として創設され、子供の年収が150万円までであれば「特定扶養控除」と同じ63万円の控除が受けられることになりました。
親の税負担を気にすることなく、子供がこれまで以上に働く事が可能になっています。
またこちらも、150万円を超える場合は、特定親族特別控除として、188万円以下までは控除の対象となります。金額は年収が上がるに連れて下がる仕組みとなっています。
●これら税制改正はどんな影響があるのか!?
・これまで自身や家族の税負担を気にしていたパート・アルバイトの主婦や学生がもっと長い時間働くことができるようになった。
・世帯全体としてみても、家計の収入を増やしつつ税負担を抑えることができる。
簡単に言うと、国民がより暮らしやすく、働きやすくなったと言えます。
●では企業目線ではどうか
・労働力が拡大: 働き控えの解消で、人員確保がしやすくなる
・コスト負担の増加:社会保険加入者増で、企業負担が増加する可能性
これらの他にも、社会保険加入要件 106万円の壁、130万円の壁も存在しますが、ここでは割愛いたします。
●まとめ
年収の壁が今回の改正で動く事になり、単純に私たちの暮らしは良くなる(良い方向に進む)ことが期待されます。
ですが、実際のところはより働けるようになった主婦層・学生層が実際に追加就労し、経済効果として波及するにはまだ少し時間がかかります。
税収への影響も少ないことから、コスパのよい経済政策として期待されている。
ということをまずは覚えておいてください。
Contact us
お気軽にお問い合わせ下さい
日本クレアス税理士法人グループでは、お悩み・課題をワンストップで解決いたします。
● 月次決算が遅い、時間がかかる
● 今使ってる会計ソフトを変更したい
● 現在の会計事務所は返事が遅い
このような課題、お悩みはございませんか?
私たちがプロフェッショナルな力でお客様の経営をナビゲートします。
是非お気軽にお問い合わせください。








